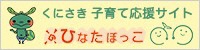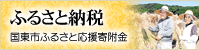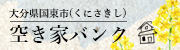本文
糸原地区の文化財

|
糸原 |
市指定 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO. |
区分 |
細区分 |
名称 |
所在地 |
所有者 |
指定年月日 |
|
01 |
史跡 |
* |
武蔵町糸原 |
個人 |
昭和46年9月6日 |
|
|
02 |
有形 |
美術工芸 |
武蔵町糸原 |
糸原区 |
昭和54年7月1日 |
|
行者原古墳群

糸原連仏の岡の塚から勝手迫、石井、行者原、府内谷に至るまでの1.5kmの間、景勝の海岸線に沿って連なる古墳群で、岡の塚を除き、そのほとんどが直径10mから20mの円墳か楕円墳である。すでに破壊されたもの、封土の流れたものなども加えて、現在までに確認されたものは40基を数えている。古墳を造る風習は‘弥生文化時代の終る3世紀の中頃から始まるが、行者原古墳は古墳時代中期から後期のもので、弥生式土器や須恵器、円筒埴輪、鉄製の剣や鏡等の副葬品が出土している。この地の古墳は、何れも海石を並べた石棺で、中に大量の朱を詰めてある点は特色というべきである。
石造役小角像

役小角(役行者)は修験道の開祖でその像は国東半島の各地に見られる。
像高は90cmで、一本歯の高足駄をはき袈裟をかけ、左手に経巻を握り、右手は以前錫杖か何かを持っていたものと思われるが現在は失われている。顔の表情は穏やかで気品に満ちている。更に注目されるのは両肩に鳥の羽の如きものが剖まれている点である。役小角が自由に空を飛べたということからであろうか。像の背面に銘文が陰刻れてり、造立つ年代は寛政元年(1789)である。叉、行者原の地名は、役小角がここで護摩を焚いて修業し、文殊山、英彦山石槌山に入る足場としたという伝説による。
近くに役小向の飛石(高さ4m)が残されている。