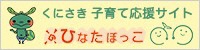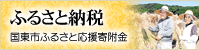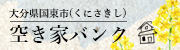本文
教育長の部屋(2025年1月)
新年を迎えて
新年明けましておめでとうございます。今年は、巳年です。巳年は、努力してきたことが一気に伸びる年であると言われています。全ての学校が、そして全ての児童生徒が飛躍の年になることを願っています。今回は、これからの学校教育のあり方について考えてみたいと思います。
○これから求められる能力
これからのAI(人工知能 Artificial Intelligence)時代では、課題解決の力より課題設定の力が必要になってきます。なぜなら、課題解決はAIが得意とする能力であり、そのAIに課題を設定することが人間の役割になるからです。
○学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)
子ども一人ひとりの豊かな学びと育ちを支え、持続可能な教育活動を実施していくためには、学校・家庭・地域が連携し協働することが重要です。そのためには、学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)を活用することが大切であると考えています。学校運営協議会制度は、平成16年度に「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みとして法制化されました。将来、社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を明確にし、それを学校・家庭・地域が共有した上でお互いにこれまで以上に連携し協働しながら学校教育を通じてよりよい社会を実現すること。すなわち、学習指導要領の柱の一つである「社会に開かれた教育課程」を実践するために、この制度は極めて有意義な組織であり、学校経営の根幹をなすものであると考えています。
○地域の子どもは地域で育てる
今から約150年前、国の学制発布の3年前、京都市では「はぐくみ憲章」が制定され、子どもを社会の宝として愛し、慈しみ、将来を託してきた人づくりの伝統が脈々として受け継がれてきました。現在では、行政や企業まで巻き込んだ市民の行動規範として様々な協働活動の礎となっているそうです。国東市においても、平成18年の合併以来「地域の子どもは地域で育てる」を基本にいろいろな施策を行ってきました。統廃合で地域の形が変わってきた学校もありますが、国東市の子どもたちには変わりはありません。それぞれの校区で読み聞かせ、学びの教室、伝統文化体験、花壇や運動場の整備や掃除等の学校支援や登下校の見守り等多岐にわたる活動を学校と共に実践していただいています。まさに地域ぐるみの教育が行われていると思っています。この素晴らしい取組を今後も継続していくことが大切であると考えています。
○子どもの学びや育ちを確かなものにするための「人づくりの輪」
子どもたちは学校だけで育つものではありません。学校・家庭・地域社会の中で友達・先生・保護者・地域の方々と関わり、自分とは異なる価値観に触れ、多様な人々と協働しながら社会的変化を乗り越えていくための土台となる「生きる力」を身に付けていきます。そのためには、大人である私たち自身も自分とは異なる立場の方を価値ある存在として尊重し、共に子どもたちを育んでいこうとする思いを持ち、子育てや教育に向き合うことが必要であると考えています。「全ては子どもたちのために、全ての子どもたちのために」という思いを学校・家庭・地域で共有できることが子どもたちの未来を明るくする一歩ではないかと思います。子どもを地域社会の宝として育む「人づくりの輪」が社会全体に広がることを願っています。