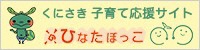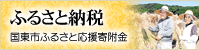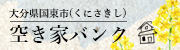本文
教育長の部屋(2025年9月)
「教師に望むこと」
(1)教育長の思い
教育長がいくら力を入れたところで、子どもたちに対する実際の指導は、学校の先生方にお願いするしかありません。したがって、これまでの指導・支援も、もしかしたら「口だけの指導」と受け止められているかもしれませんが、願わくば教育に携わるひとりの先輩としての願いとして受け止めていただけるとありがたいと思っています。
(2)子どものつぶやきを大事に
「子どものつぶやきを大事に」ということをよく聞くと思いますが、私も教諭時代に先輩たちからよく言われてきました。「子どものつぶやきが聞こえる。それは『小学校一級 (一種) 普通免許状』よりも、もっと大切な免許状なのだ。」と。また、「子どものつぶやきの聞こえなくなっている先生は、先生の資格があるとはいえない」とも言われた経験があります。
教育研究の第一人者である『北 俊夫』氏は、ある冊子の巻頭言にこう書いています。
『・・・教室には、「なるほど」「どうしてかな」「どうしよう」などとひらめいたことをその場の状況を気にせずにつぶやく子どもがいる。内容は喜怒哀楽の感情だったり、疑問や知的な活動の一端だったりする。それらの内容は意図して発言した時と比べるとかなり本心に近い。つぶやく行為は自己内対話でもある。必ずしも周囲を意識していない。つぶやきが発せられるのは、その子どもが対象に主体的に関わっている証だと受け止めたい。つぶやきが聴かれる学級は、子どもたちが伸び伸びしている。学びにも深まりを感じる。つぶやきは、授業の質や方向を定める貴重な教材である。にもかかわらず、「しばらく黙っていなさい。」などと制してしまうことがある。子どもの育ちや学びを摘み取っていることにならないだろうか。最近、つぶやきの価値に気づいている教師や子どものつぶやきに耳を傾け活かそうとしている教師が少なくなったように思う。子どもの何気ないつぶやきが聞こえる教師は、一人ひとりの子どもに耳を傾け、つぶやきをもうひとつの教材として活かそうとしている。つぶやきに敏感になることは、学習指導の場面だけではない。生活の中でも、子どもの何気ないつぶやきを拾いその背景や意図を洞察する力量を身につけたい。つぶやきは日常指導にも活かすことができる。日々の教育活動で、つぶやきの持つ教育的な価値を認識し、子どものつぶやきを聞き入れ、活かすことのできる教師をめざしたい。』
教育研究者の言葉ですので、本質をついているのは当然ですが、実践している現場の教師もそう感じている先生は多いのではないでしょうか。私たち大人だって気付いたり発見したりすれば嬉しくて黙っていられません。「みんなに聞いてほしい。先生に認めてほしい。」と思うのではないでしょうか。そういう子どもたちの思いを受け止めながら、うまく本時の活動のねらいに近づけていくことが大切だと思います。教師の敷いたレールに無理やり引き込むのではなく、子どもの発想に寄り添いながら繋げていくことが教師の指導力であると思っています。
※ これは、私が校長時代に先生方に伝えたことの一つです。発表できる子どもだけで進めていく く授業ではなく、学級全員の思いを大事にしながら進めていく姿勢を教師が見せることで、子どもたちが学級の一人ひとりを大事にする集団に変わっていきます。それぞれの学校で、今一度、自分の実践を振り返り、子どもの教育に携わって頂きたいと願っています。