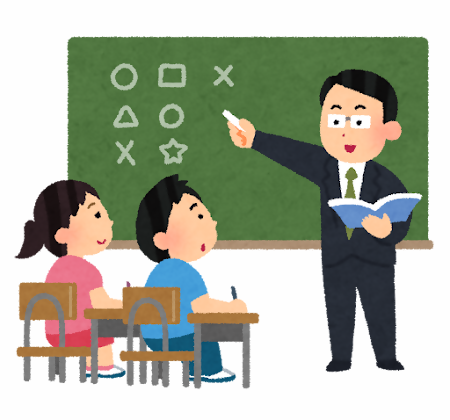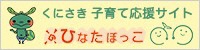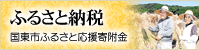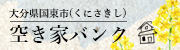本文
教育長の部屋(2025年11月)
「指導者としての授業観」
今年度も10月27日~11月4日にかけて文教厚生委員・教育委員の学校訪問がありました。
校長による熱のこもった学校経営の説明や、真剣に学習に取り組んでいる児童生徒の授業参観を通して意見交換を行いました。
今回は授業のあり方について考えてみたいと思います。
1.授業とは
授業の成否は、子どもによって決まります。教師が準備した教材を受け入れているかどうかです。
子どもたちが教師の授業を受け入れるからこそよい授業を行う関係性が生まれます。
子どもが受け入れられないのは、「難しすぎる」「唐突すぎる」「日頃の人間関係ができていない」からです。
子どもたちがいったん受け入れれば、自ら詳しく調べたり、考えたり、話し合ったりして、自分のものにしていきます。
疑問が明確になり、自分なりの考えを持って、理解が深まるのです。
授業は、「教師」と「子ども」と「教材」の3つで構成されています。そして、それらは一定の距離があります。この距離感が大切なのです。
いったん受け入れられると子どもは教材(学習内容)を自分のものにして、思考や理解という形で教師に返すというよい循環が生まれます。
そのためには、まず子どもたちが「教材」を受け入れられるように興味・関心を引き出したり、問題意識を高めたりしようとする手立てが必要です。
また、子どもたちに化学反応を起こさせ思考や理解が深まるような仕掛けをすることも大切です。
「教材」と「子ども」の距離を縮めれば授業がうまくいくことを教師は学んでいます。だから、子どもの存在を意識し、準備する教材(内容)を考えるようにするのです。
教育(授業)の成果は子どもたちの状況によってしか測れないからです。
2.教師としての心の立ち位置
教室では、教師と子どもは向かい合わせに立っていますが、心の立ち位置は、子どもの側から同じ方向で立つことが大切です。
1.子どもの目線に立つようにしたい
子どもの目線に立つということは、子どもの立場から指導内容を見直すことです。具体的には「授業が難しくて分らないよ」目線です。「分からないから授業する」「分かるように指導する」ことが教師の最大のミッションです。教師は、心の中に「厳しい指導者」と「分からない子ども」を同居させることが必要です。「分からない子ども」がいるからこそ、「どうしたら、その子が分かるようになるか」という「問い」を持ち続けられます。そんな教師こそができる教師です。
2.子ども同士のつなぎ役を担う
なぜ、子どもをつながなければいけないのでしょうか。大人の理論である教材を子どもに落とし込むためには、自分の言葉で内容を表現できるようにしなければなりません。そのためには、分からないことは「分からない」と発言できることや分かったことは「自分の言葉で具体的に表現できる」ことが大切です。授業の中では、いくつも子どもたちの言葉を重ね合わせる必要があります。子ども達が自分の言葉で思いを表現し、その発言を束ねることで、概念的理解へと進みます。こういう学び合いのプロセスがなければ理解できないし、定着もしません。
3.事前の準備の大切さを実感する
授業には準備が必要です。「ねらい」がしっかり定まっていれば、そう間違った方向へは行きません。授業前に頭の中でシミュレーションすることが大切です。
3.自分の中にモデルを創る
他者の授業は自分を映し出す鏡です。教師には親方や師匠がいません。厳しくも言われません。だとすれば自分自身の力で磨くしかありません。自分の中に親方や師匠を創るしかないのです。