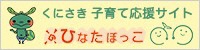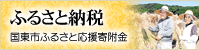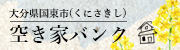本文
教育長の部屋(2024年9月)
子どもたちの発達に大切なこと
人間は、今この瞬間を楽しみつつ、未来にも備えています。二面的な存在です。今を優先しすぎると未来の可能性が閉ざされる一方で、未来を優先しすぎると今がなおざりになります。そのバランスをとることは容易ではありません。しかし、今、子ども達に、大きな格差が見られるようになってきました。本来、今を楽しみつつ、未来にも備える子どもが、「今を生きる」子どもと「未来に向かう」子どもに分かれてしまっているのです。その原因は何でしょうか。幼児期には、子どもの様々な能力が開花し、そこには大きな個人差があります。学力は子どもの一側面にしか過ぎません。そこだけに注目するのはあまり意味がありません。学力をめぐる議論は、小学生以上の子どもしか論じることができないのです。しかし、子どもの発達の根っこは幼児期にあります。年齢に応じた諸々の発達の後に知的学力をつけさせたいものです。
発達とは、身体や行動、精神、脳における時間に伴う変化のことです。子どもの発達には、標準的な成長過程が見られます。ところが、標準的というのは、半数程度が達成できるものに過ぎず、実際にはその通りの経過をたどらない子どもも多いということです。発達には個人差があるということです。通常、この個人差はあまり問題にはなりませんがいくつかの能力の個人差には、子どもの将来に重要な影響を与えるものがあります。
ジェームス・ヘックマン博士は、子どもの頃のどのような能力が大人になってからの健康状態・年収・職業などと関連するかを調べたそうです。その時に注目した能力が「自制心」だそうです。「自制心」とは、目標に向かって自分をコントロールする力の事です。「自制心」が強い人は、目の前の障害に惑わされず目標を達成することができます。いわゆる「未来に向かう」ことができる人なのです。健康面では、肥満や高血圧になりにくく、経済面では、年収が高く、貯蓄の額も大きいそうです。「自制心」が強いと、友達の誘いやゲームなどに惑わされず、勉強や仕事に集中することができるのです。
5歳半の調査では、「落ち着いて話を聞く」「ひとつのことに集中する」「がまんする」の項目で「できる」と回答したのは7割から8割だったそうです。「自制心」以外にも子どもの将来に大きな影響を与える能力に「他者を思いやる心」があります。相手の困った様子をみて自発的になされるのが「思いやる行動」です。オーストラリアで5万人を対象にした研究で、5~6歳の頃に「思いやる行動」ができる子どもは、同時期の学力が高く、その結果9歳頃の学力が高いことが示されています。友だちに親切な子どもは、学力を高めやすいということが言えるのです。
先にも述べましたが「自制心」とは、自分をコントロールする力です。この力が発達するということは「今を生きる」ことよりも「未来に向かう」ことを選ぶということです。「思いやる行動」がとれるということは、「今、自分がしたいこと」よりも「他者を優先すること」を選択できることです。そして、他者を優先することは、未来への投資と理解できます。「自制心」が弱く、「思いやる行動」をしにくい子どもと、「自制心」が強く、「思いやる行動」ができる子ども、「今を生きる」子どもと「未来に向かう」子どもに分かれているのではないかと思われます。脳の前頭前野の働きも大きくかかわってきます。この前頭前野は、5歳から6歳頃の幼児が最も強く活動させているそうです。